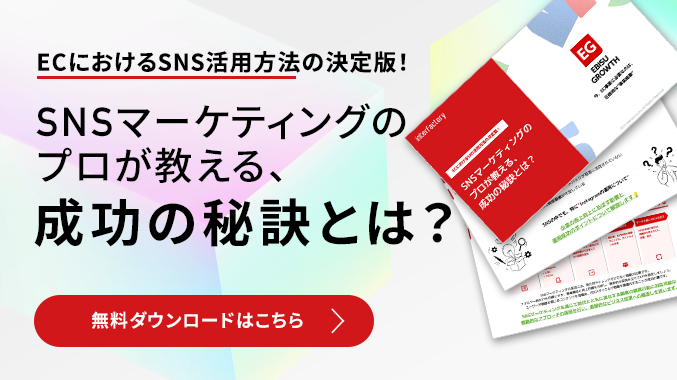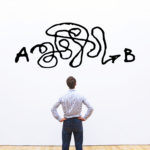TikTokでバズを狙っている人なら、「どんな時間帯が一番再生数が伸びるのか知りたい」と考えているのではないでしょうか?
TikTokと言えば、ひと昔前は10代のユーザーがほとんどのSNSといったイメージでしたが、現在では幅広いユーザーが利用するようになり、ターゲットごとに伸びる時間帯は異なります。総務省のデータによると、TikTokの利用率は日本国内で32.5%であり、年代別の利用率は以下のとおりです。
◆年代別TikTokの利用率
20代:52.1%
30代:32.0%
40代:26.8%
50代:25.4%
60代:13.0%
出典:総務省「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」(2024年6月)
このため、ターゲットを意識しないのであれば、一般的にゴールデンタイムとされる夜21時以降を狙って投稿するだけで良いのですが、Tiktokがこれだけ幅広い層に利用されていることを考えると、ターゲット別に投稿が伸びる時間を意識すべきです。
この記事では、forUSERS株式会社でマーケティングを担当している筆者が、TikTokの伸びる時間帯をターゲット別に詳しく解説します。
【ターゲット別】TikTokの再生数が伸びやすい投稿時間帯
TikTokクリエイター向けの公式Tipsにおいても「フォロワーがアクティブな時間」を確認することが推奨されております。そのためターゲット別に投稿を狙う場合でも、スマートフォンから離れていることが多い時間を避けて、スマートフォンで時間を潰している時間帯を狙って投稿しましょう。
◆ターゲット別TikTokの伸びる時間帯
| ターゲット層 | 平日 | 土日 |
| ①中高生 | 17時〜19時/ 21時以降 | 10時〜12時/ 21時以降 |
| ②大学生 | 12時〜14時 / 22時以降 | 21時〜24時 |
| ③社会人 | 7時〜8時(通勤中) / 12時〜13時(昼休み) / 帰宅後の20〜22時 | 11時〜13時 / 20時〜22時 |
| ④主婦 | 10時〜11時 / 14時〜15時 / 21時〜22時 | 夕食後の20〜22時 |
この表は、ターゲット別の日常の行動パターンを踏まえて、筆者が独自に作成したものです。
この表を見ると、どのターゲットであったとしても平日、土日を問わず21時以降であれば、スマートフォンでアクティブな可能性が高く、最もTikTokが伸びやすい時間帯とも言えます。そのため、まずは21時の投稿が基本となります。
それでは、各ターゲットごとにTikTokが伸びる時間を解説します。
① 中高生向けの場合
◆おすすめ時間帯
土日:10時〜12時/ 21時以降
中高生の場合のピークは、平日の部活や塾が終わった夕方〜夜となります。学生であるため遅くまで起きていないので、夜は21時がピークタイムとなります。土日の場合は、比較的自宅にいる午前中が狙い目ですが、やはり土日においても、21時以降が暇つぶしの時間においてはピークタイムと言えるでしょう。
②大学生向けの場合(生活リズムが自由)
◆おすすめ時間帯
週末:夜21時〜24時
大学生の場合は、講義の合間(昼休みや空き時間)にスマートフォンを息抜きで視聴する傾向があります。講義がない場合や講義後は、多くの学生はアルバイトに従事しています。そのため、帰宅後に夜ふかしを行うことが多く、深夜が最もアクティブな時間となります。
③社会人向けの場合(通勤や昼休みにスマートフォンを使う)
◆おすすめ時間帯
土日:11時〜13時 / 20時〜22時
若いビジネスパーソンは、通勤時間に電車でTikTokを見ているケースが多く、社会人には非常に狙い目な時間帯と言えます。夜は「寝る前のリラックスタイム」に短時間動画で時間を消費する人も多く、筆者自身もまさにこのタイプであり、21時~24時の寝るまでにTikTokで多くの動画を視聴します。
最近では10~30分の長い尺の動画も出てきており、YouTubeのように動画を楽しむことができます。
④主婦向けの場合(家事の合間にスマートフォンを使う)
◆おすすめ時間帯
週末:夕食後の20〜22時
平日の日中は、午前中の家事が終わった後や子どもが昼寝する時間、夜は子どもの寝かしつけ後の「自分時間」が、主なTikTok視聴時間となります。週末は家族で出かけることが多いため、夕食後の20時以降が狙い目となります。
このように、どのターゲット層も21時以降が狙い目ですが、それ以外にもターゲットごとに有効な訴求時間があります。
それでは、次にTikTok動画投稿の7つのポイントを解説するので、TikTokの視聴率を伸ばそうと考えている方はしっかり押さえておきましょう。
TikTok動画投稿の7つのポイント
それでは優先度が高い順にTikTokの7つのポイントを解説します。
ポイント① 冒頭3秒で引きつける構成にする
ユーザーは最初の数秒でスワイプ(次の動画を視聴)するかを判断します。この冒頭の数秒間に「驚き・笑い・問いかけ」など、ユーザーの注意を強く引く要素を持ってくるようにしましょう。
例えば、以下は株式会社BEEMのTikTok動画ですが、ユーザーの興味を引くワード、テンポなど、冒頭での訴求を強く意識しているのが分かります。
◆冒頭の訴求を意識した投稿動画(BEEM)

このように、ユーザーのスワイプする指を止めるような工夫を考えましょう。このような動画をつくためには、すでにTikTokで成功しているTiKtokerを参考にして、自分の動画にも取り入れてみるべきです。
ポイント② 動画は短くテンポよく
TikTokは基本的に「スキマ時間に見る」メディアです。無駄な間を省き、テンポよく進行することで離脱を防げます。昨今は10分を超える動画も流行っていますが、まずは動画の目安は15~30秒以内だと、ユーザーが飽きないで動画を最後まで視聴することができます。
動画を短くテンポよく作るためには、最初の3秒にインパクトを持たせることが重要です。冒頭で興味を引く言葉や映像を入れることで、ユーザーのスクロールを止めることができます。また、カットを細かく入れてテンポを生む編集や、テロップで情報を補足する工夫も効果的です。
ポイント③ テロップと字幕を活用する
音声を聞かずに見ているユーザーも多いため、内容はすべて文字でも伝える設計が大切です。特に要点は目立つテロップにすることで理解度が上がります。また、音声を聞いているユーザーにとっても、聞き取りづらい部分はテロップにより補完されるため、テロップ・字幕は必須と言えます。
以下の動画をご覧ください。弊社forUSERS株式会社のYouTubeのショート動画ですが、テロップ・字幕のポイントはTikTokと同様です。
◆テロップ・字幕を全編に入れた動画(forUSERS)※音量注意
TikTok動画に文字を入れるには、アプリ内の「テキスト」機能を使うのが一般的です。動画編集画面で「テキスト」を選び、好きな位置に文字を配置するだけで簡単にテロップを追加できます。また、表示時間の設定機能を使えば、話のタイミングに合わせて文字を切り替えることも可能です。
さらに、伝えたい要素ごとに色やフォントを変えることで、視認性と印象に残る効果が高まります。たとえば、強調したいキーワードは太字や黄色、補足情報は白字で小さめにするなど、視線の流れを意識したデザインがポイントです。
テキストの表示に合わせて効果音を入れるのも効果的です。
ポイント④ トレンド音源やハッシュタグを取り入れる
TikTokはアルゴリズムで再生数が左右されやすいため、人気のBGMや流行のタグを活用することで、露出が増えるチャンスとなります。
特に、トレンド音源はユーザーの「おすすめ(For You)」欄に載りやすくなる要素の一つです。再生数が多い音源を使えば、それだけで動画の表示機会が広がる可能性があります。また、視聴者がすでに耳なじみのある音楽を使うことで、自然と興味を持たれやすくなるというメリットもあります。
一方、ハッシュタグは動画の内容やターゲットに応じて適切なものを選ぶことが大切です。単にトレンドタグを並べるのではなく、
#5秒で学べる
など、検索ニーズに寄り添ったタグを加えることで、アルゴリズムだけでなくユーザーにも刺さりやすくなります。トレンドは日々変わるため、TikTokアプリ内の検索バーや「人気の音源・タグ一覧」を定期的にチェックしましょう。
ポイント⑤ 世界観を統一する
投稿ごとに雰囲気がバラバラだとフォローにつながりません。ブランドやキャラの「世界観」を統一して、誰向けのアカウントかが一目で伝わるようにしましょう。
たとえば、色味・BGM・テロップのフォントや話し方などを一定のルールでそろえることで、視聴者は安心して継続視聴・フォローしやすくなります。特にTikTokでは、アルゴリズムによって過去の投稿を知らない人にも動画が届くため、どの投稿を見られても「この人(ブランド)、他の動画も気になる」と思わせる仕掛けが必要です。
具体的には、
・決まったオープニング・エンディングの構成
・キャラ設定や語り口調をブレさせない
など、視覚・聴覚・言語のすべてで一貫性を意識しましょう。
また、プロフィール文や固定投稿にも世界観を反映させることで、アカウント全体の印象が強化され、初見のユーザーにも伝わりやすくなります。
ポイント⑥ 投稿時間と頻度を意識する
ユーザーがよく見る時間帯(昼休み・夜21時台など)に合わせて投稿することで、視聴数の初動が伸びやすくなります。また、週3〜5回の安定投稿が理想です。
TikTokのアルゴリズムは、投稿直後のエンゲージメント(再生・いいね・コメント)を重視する傾向があります。そのため、ターゲットユーザーがアクティブな時間帯に投稿することで、より多くの人の「おすすめ」に表示されやすくなります。
たとえば、学生がターゲットであれば「放課後〜夕方」、社会人がターゲットなら「昼休み」や「夜のリラックスタイム」に投稿するのが効果的です。TikTokの「プロアカウント」に切り替えると、フォロワーのアクティブ時間帯データも確認できるため、投稿戦略に生かしましょう。
また、投稿頻度は多すぎても少なすぎても逆効果です。無理なく続けられる頻度で、継続的に発信し続けることが、アカウントの成長には不可欠です。投稿数が蓄積されることで、アルゴリズムからの評価も徐々に高まり、過去動画の再生も伸びやすくなります。
ポイント⑦ コメントや保存を促すアクションを入れる
「あなたはどう思いますか?」「保存しておいてね」など、ユーザーの反応を引き出す一言を入れることで、エンゲージメントが高まりやすくなります。
TikTokでは、コメント数や保存数も動画の評価指標として扱われています。視聴者のリアクションを増やすことは、より多くの人の「おすすめ」欄に表示されるチャンスを広げることにもつながります。
コメントを促す際には、意見を言いやすい質問形式や、二択の問いかけが効果的です。
「〇〇って共感できますか?」
といった形で、気軽に参加できる空気感を作ると反応が得られやすくなります。
また、情報系やハウツー系の動画では「後で見返したい」と思わせる内容に加え、「保存してね」と一言添えることで、保存数の向上が期待できます。これによりアルゴリズムからの評価も高まり、さらなる拡散につながる好循環が生まれます。
TikTok投稿の4つの注意点
ここからはTikTok動画投稿の主な注意点を解説しますので、特に初めて投稿するという方は、必ずこれらの注意点を意識してみましょう。
注意点① 著作権のある音源や映像の無断使用
TikTok内で提供されている音源は使用OKですが、外部から取り込んだ音楽や映像を無断で使うと著作権侵害の対象になります。
特に企業アカウントでは、商用利用NGの音源もあるため要注意です。たとえTikTok内で人気の音源であっても、企業や商品の宣伝に使うと規約違反になる場合があります。また、テレビ番組の切り抜きや、他人が撮影した動画の転載なども同様に、著作権・肖像権の問題が発生するリスクがあります。
安全に運用するためには、
・音楽は著作権フリー素材サイトや自作音源を活用する
・映像素材もオリジナルか、ライセンスを確認済みのものを使う
といった対応が重要です。
企業アカウントで炎上・削除を防ぐためにも、制作前にコンテンツの権利関係をしっかり確認する体制づくりを心がけましょう。
参考:Tiktok 著作権
注意点② 他人の顔や子どもの映り込み
撮影中に他人の顔が映り込んでいると、プライバシーの侵害や肖像権の侵害になる可能性があります。特に公共の場所やイベント会場などでは、背景に通行人が映るケースも多く、意図せずトラブルを招くこともあります。
また、子どもを撮影する場合は、必ず保護者の同意を得ることが必要です。見た目だけでは年齢を判断できないため、少しでも年齢が低く見える人物を撮る場合は、慎重な対応が求められます。
企業アカウントやインフルエンサーとしての投稿では、特に注意が必要です。無断で他人の顔が映っていた場合、動画の削除要請だけでなく、信頼性の低下や炎上リスクにもつながります。
安全に運用するためには、
・モザイク処理やぼかしを活用する
・出演者には必ず事前に許諾を取り、同意書を交わす
といった対応を徹底しましょう。
注意点③ センシティブな話題や差別的表現
宗教・政治・容姿・性別・病気などに関する表現は、意図しなくても批判や炎上を招く可能性があります。
特にネタ系やジョークを交えた動画であっても、見る側によっては不快に受け取られたり、差別的と感じられる場合があります。たとえ軽い気持ちの投稿でも、誤解を生んでしまえば企業や個人の信用に大きなダメージを与えるリスクがあります。
また、TikTokではグローバルなユーザーが多く、文化や価値観の違いも影響します。国内では許容される表現でも、他国の視聴者にとってはセンシティブな内容になることもあるため、慎重な配慮が必要です。
炎上を防ぐためには、
・表現が誰かを傷つけていないか事前にチェックする
・公開前に第三者の目で内容を確認してもらう体制を作る
といったリスク管理を行いましょう。
注意点④ 商品レビューや広告は「PR」表記が必要(企業・インフルエンサー)
ステルスマーケティング(いわゆるステマ)は、消費者の信頼を損なう行為であり、現在はガイドライン違反として明確に禁止されています。
企業から報酬や商品提供を受けて紹介する場合は、投稿内に「#PR」「#広告」などの表記を明記する義務があります。これは企業アカウントに限らず、インフルエンサーや個人クリエイターであっても同様です。
特に最近では、消費者庁によるステマ規制の法制化も進み、違反した場合は行政処分の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
安全に運用するためには、
・PRであることが視認しやすい位置に表示されているか確認する
・投稿の冒頭またはキャプションの冒頭に明示するのがベスト
ユーザーとの信頼関係を築くためにも、正直で透明性のある情報発信を心がけましょう。
まとめ
TikTokは、投稿時間を最適な時間にしたところで、必ず再生数が伸びるものではありません。それにはユーザーを引きつける魅力的なショート動画を作る必要があります。
本記事で解説した7つのポイントを意識して、試行錯誤を繰り返しながら投稿を継続することが重要です。
もし、自社のTikTokアカウントの本格的な運用をお考えであれば、株式会社インターファクトリーのECコンサルティングサービス「EBISU GROWTH(エビス グロース)」の活用をご検討ください。経験豊かなECコンサルタントが、TikTokも含めたSNSマーケティングのサポートを行います。
以下のEBISU GROWTH 公式サイトより、お気軽にお問い合わせや資料をご請求ください。