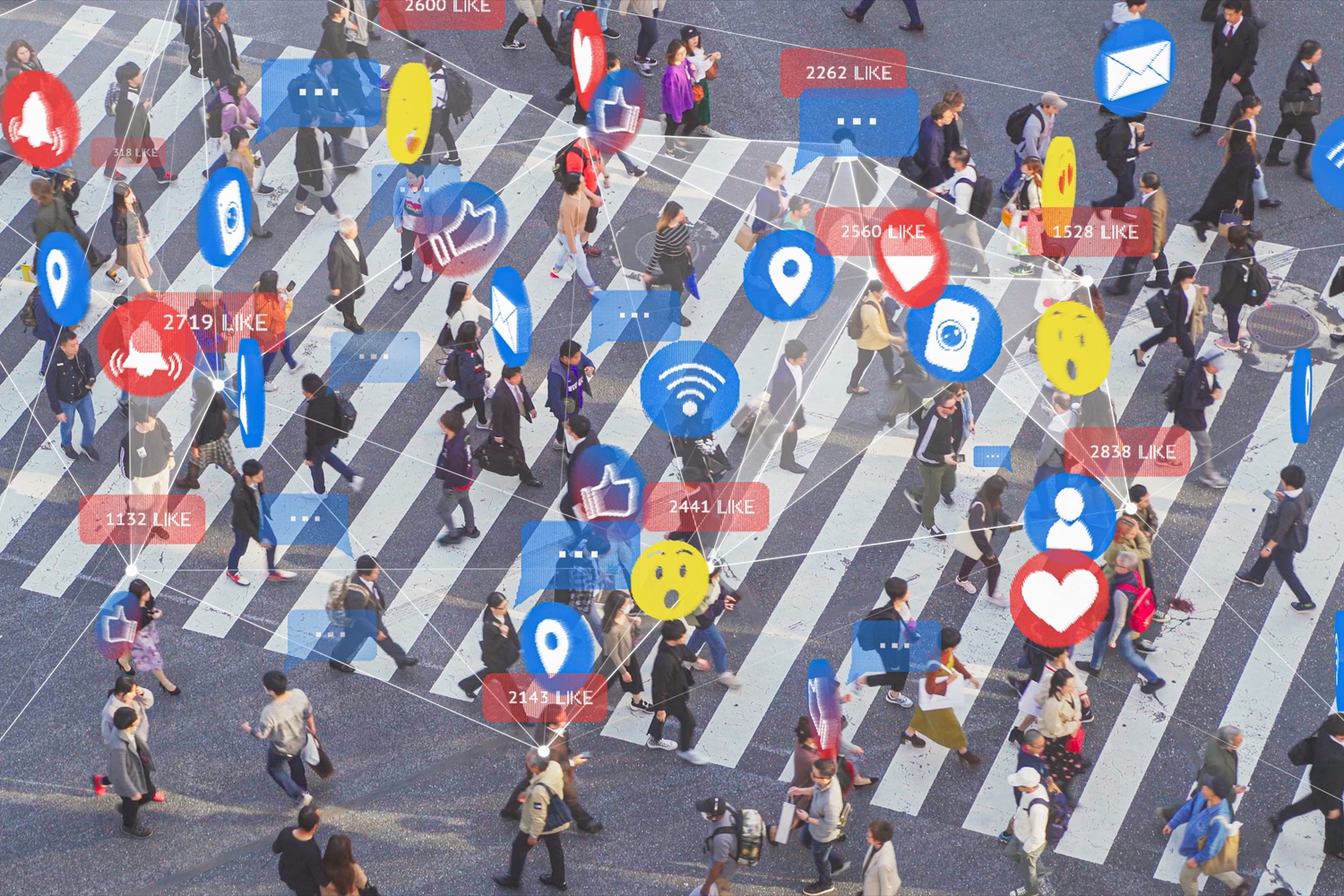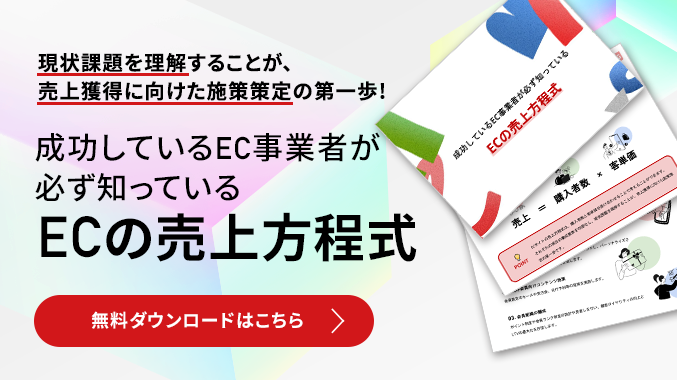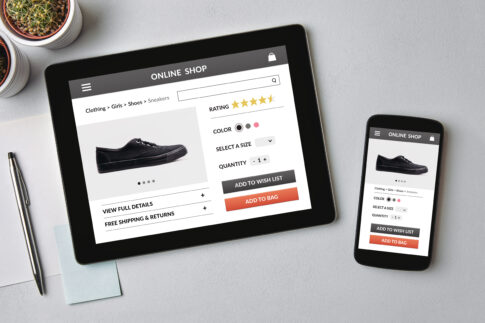コミュニティマーケティングとは、ブランドやサービスの理念や世界観に共感する顧客と双方向の関係(コミュニティ)を築き、信頼と共感を基盤にブランド価値を高めるマーケティング手法を指します。
SNSの普及や消費者意識の変化により、従来の広告的アプローチだけではブランドの支持を得ることが難しくなりました。
その一方で、企業や自治体が顧客・利用者・地域住民と共に価値を育てる取り組みが増え、長期的なブランド成長につながる重要な施策として評価されています。
この記事では、forUSERS株式会社でマーケティングを担当している筆者が、コミュニティマーケティングを以下の5つのタイプに分類し、それぞれの特徴と、どのような事業に相性が良いのかを具体的に解説します。
◆コミュニティマーケティングの5つのタイプ
② オンライン・交流型
③ ナレッジ・共創型
④ 理念・ブランド共感型
⑤ ロイヤルティ・会員型
これらの代表的な事例も交えながら、各タイプの特徴と成功のポイントを解説していきますので、企業のブランド成長戦略を考えるヒントとして、ぜひ参考にしてください。
コミュニティマーケティングの5つのタイプと、それぞれに向いている企業とは?
コミュニティマーケティングは、その目的や運営の形態は企業によってさまざまです。商品購入を目的とした短期的な施策ではなく、顧客との関係を長期的に育てる仕組みであるため、自社の事業内容やブランド特性に合った手法を選ぶことが成果につながります。
ここでは、コミュニティマーケティングを5つのタイプに分類し、それぞれの特徴と向いている業種・組織タイプについて解説します。
◆コミュニティマーケティングのタイプ一覧
| タイプ | 主な目的・特徴 | 主な手法・媒体 | 向いている企業・組織 |
| ①体験・イベント型 | 顧客とのリアルな接点を通じて体験価値を共有し、絆を深める | ・ファンイベント ・キャンプ ・ワークショップ ・店舗イベント |
・アウトドア ・アパレル ・ライフスタイルブランド |
| ②オンライン・交流型 | デジタル空間での継続的な交流を軸に関係を構築する | ・SNSコミュニティ ・Discord ・LINEオープンチャット ・フォーラム |
・SaaS ・D2C ・若年層向けブランド |
| ③ナレッジ・共創型 | 顧客やユーザーの知見を共有し、新たな価値を共に創り出す | ・勉強会 ・ユーザーグループ ・共創プロジェクト ・投稿プラットフォーム |
・IT ・教育 ・BtoB ・スタートアップ |
| ④理念・ブランド共感型 | ブランドの理念や世界観に共感するファンを育て、価値観を媒介に結び付ける | ・オウンドメディア ・SNS ・アンバサダー制度 |
・コスメ ・食品 ・サステナブル系ブランド |
| ⑤ロイヤルティ・会員型 | 会員制度や特典を通じて顧客の帰属意識を高める | ・会員制コミュニティ ・リワード制度 ・サブスクリプション |
・小売 ・飲食 ・リピーター商材全般 |
以下に、それぞれのタイプについて詳しく解説します。
タイプ① 体験・イベント型
リアルな場での体験を通してブランドへの共感を生むタイプです。実際に体験することで記憶に残りやすく、商品を超えた「ブランド体験」が形成されます。
このタイプは、特にアウトドア・アパレル・インテリアなど、世界観を体感できるブランドに適していますが、運営コストや地域的制約があるため、オンライン施策と組み合わせることが効果的です。
タイプ② オンライン・交流型
SNSやチャットツールなどのオンライン空間を中心に構築されるタイプです。顧客同士の交流が継続しやすく、企業はその場をファシリテーター(促進者)として運営します。
このタイプは、特にデジタルネイティブ層をターゲットとするD2CブランドやSaaS企業に向いています。情報共有・共感形成がスピーディで、顧客との距離を短く保てるのが強みです。
タイプ③ ナレッジ・共創型
顧客が単なる消費者ではなく「共創者」として関わるタイプです。製品改善のアイデア募集や、ユーザー会などを通じて、知識を共有し合いながら新たな価値を生み出します。
このタイプは、IT業界、教育分野、BtoB企業など、専門知識やノウハウを扱う業種に適しており、顧客エンゲージメントの向上とイノベーション促進の両立が期待できます。
タイプ④ 理念・ブランド共感型
ブランドの理念や社会的なビジョンに共感した顧客が、自発的に支持・発信していくタイプです。購入動機が「共感」や「価値観の一致」に基づくため、短期的な販促よりも長期的な信頼関係の構築に向いています。
このタイプは、サステナビリティやエシカル消費、社会貢献などをテーマに掲げるライフスタイル系のブランドとの相性が高いです。
タイプ⑤ ロイヤルティ・会員型
ポイント制度やメンバーシッププログラムなどを通じて、顧客の帰属意識を高めるタイプです。特典や限定イベントを提供することで、長期的な利用・再購入を促進します。
このタイプは、小売業・飲食業・美容サービスなどリピートビジネスに最も適しており、CRM(顧客関係管理)と組み合わせることで安定した売上基盤を築けます。
このように、コミュニティマーケティングは「どの接点を重視するか」「どの関係性を育てたいか」によってアプローチが異なることが分かります。
それでは、これら5つのタイプの具体的な事例を紹介します。
タイプ別のコミュニティマーケティング実践事例7選
ここでは、前項で紹介した5つのタイプのコミュニティマーケティング実践例として、自治体や国内企業による取り組み事例を7つ紹介します。
事例① 北海道下川町
タイプ① 体験・イベント型

北海道北部の下川町は、人口約3,000人の小規模自治体ながら、「関係人口」をキーワードに、地域内外の人々が継続的に関わる仕組みを早くから整えてきた自治体です。行政・地域団体・住民が一体となって、地域ブランディングの一環としてコミュニティ的アプローチを用いたマーケティング施策に取り組んでいます。
象徴的な取り組みが、オンラインコミュニティ「シモカワつながりLab」です。このコミュニティは、移住検討者や地域に関心を持つ人々が、町民や関係団体と交流できるプラットフォームとして運営されています。
生活・仕事・子育てといったテーマごとに情報が共有され、参加者が互いに質問・意見交換を行うことで、下川町に関わる多様な人々がゆるやかにつながる場となっています。
また、地域イベントや移住体験プログラムやワークショップを通じて、町外の参加者が実際に地域に足を運び、住民と顔を合わせながら関係を深める仕組みも展開しています。
このように、下川町はオンラインとリアルの両面で、「訪れる」「関わる」「暮らす」という多層的な体験を設計しており、行政が一方的に情報を発信するのではなく、住民・参加者が主体的に地域づくりに関わることで、地域そのものがひとつの「共創型コミュニティ」として機能しています。
地域というブランドを媒介に、外部の人々が自発的に関わり続ける構造を築いた下川町の事例は、自治体におけるコミュニティマーケティングの先進モデルと言えます。
参考 / 画像引用:北海道下川町ホームページ、北海道下川町移住移住情報サイト タノシモ(tanoshimo)
事例② カゴメ株式会社
タイプ② オンライン・交流型

カゴメ株式会社は、顧客(ファン)との関係性を深めるために、2015年に公式ファンコミュニティサイト「&KAGOME(アンドカゴメ)」を開設しました。単なるキャンペーンサイトではなく、ファンが自ら参加・発信できる常設型のプラットフォームとして運営されています。
会員数は2024年時点で約6万人に達し、レシピ投稿や商品レビュー、アンケートへの参加を通じてユーザーが意見を発信できる仕組みを整備しています。
ブランド側は投稿データやコメントをもとに、商品開発や販促施策にフィードバックしています。このような活動により、ファンとブランドの双方向の関係性が日常的に生まれています。
また、コミュニティでは、「食やレシピ」を共通テーマに、ブランドと顧客がゆるやかにつながる場を設けています。ここでは、企業側が一方的に情報を発信するのではなく、顧客に対して「食を楽しむ仲間」という感覚を重視することで、ブランドと顧客の心理的距離を縮める設計になっています。
カゴメの事例は、オンライン上の継続的な交流を通じてブランドとの接点を維持する、デジタル時代のコミュニティマーケティングの好例です。顧客の声を可視化し、企業と生活者が共にブランドを育てていく循環を確立した点に大きな特徴があります。
参考 / 画像引用:みんなとカゴメでつくるコミュニティ &KAGOME(アンドカゴメ)
事例③ CAINZ
タイプ③ ナレッジ・共創型

ホームセンターチェーンのCAINZ(カインズ)は、「ともに、くらしをDIYする」というブランドビジョンのもと、顧客と共に生活アイデアを共有・創造するコミュニティ形成に取り組んでいます。
2021年には、DIY愛好者を対象としたオンラインコミュニティ「CAINZ DIY Square」を開設し、ユーザーが自身の作品を投稿したり、他の会員と意見交換を行ったりできるプラットフォームを運営しています。
このコミュニティでは、投稿・コメント・フォローなどの行動がポイントとして蓄積され、ランクアップ制度を通じて参加意欲を高める仕組みを採用しています。会員同士が互いの作品を見て学び合うだけでなく、社員がコメントで助言するなど、ブランド側も積極的に交流を行っています。
また、カインズ実店舗でのワークショップやイベントと連動し、オンラインとオフラインの両面で顧客接点を強化しています。
カインズの取り組みは、購買の前後で顧客と継続的に接点を持ち、ブランドと共に「学ぶ」「つくる」「共有する」という体験を通じて関係を深める点に特徴があります。
製品中心の販売モデルから、顧客同士が互いに刺激を受け合う「共創型コミュニティ」へと発展しており、これが結果としてブランドへの信頼や再訪率向上につながっています。
参考 / 画像引用:CAINZ DIY Square
事例④ Japan AWS User Group(JAWS-UG)
タイプ③ ナレッジ・共創型

JAWS-UGは、Amazon Web Services(AWS)のユーザーによって運営される日本最大級の技術コミュニティです。
2010年の発足以来、全国に60以上の支部を展開し、年間数百回を超える勉強会やイベントを開催(2022年は年間390回以上)しています。参加者数はのべ20,000人以上に達し、技術者同士の知見共有を軸に、企業・個人を問わず幅広い層が関わる活動として発展してきました。
特徴的なのは、AWS Japan(提供企業)が主催者ではなく「支援者」として関わっている点です。イベント企画や登壇者の選定、学びのテーマ設定はコミュニティメンバー自身が担い、AWS Japan は会場提供や技術支援などを通じてサポートする形を取っています。
この自律的な運営体制により、ユーザー同士が課題や知見を共有し合い、新しい技術活用や事例が次々と生まれるナレッジ・共創型コミュニティマーケティングが実現しています。企業発信によるトップダウンのマーケティングではなく、ユーザー同士の協働によって信頼と価値が自然に広がっていく構造です。
JAWS-UGの事例は、BtoB領域におけるコミュニティの理想形と言えます。ユーザーが主体的に知識を共有し、企業はその共創を支援することで、ブランド理解と利用促進を同時に実現しています。
参考 / 画像引用:JAWS-UG(AWS User Group – Japan)
事例⑤ 北欧、暮らしの道具店
タイプ④ 理念・ブランド共感型

株式会社クラシコムが運営する「北欧、暮らしの道具店」は、2007年に北欧ヴィンテージ雑貨を主軸とするECサイトとしてスタートしましたが、今では単なるECではなく、自社を「ライフカルチャープラットフォーム」と定義し、雑貨・衣料・インテリアに加えて、Web記事、ポッドキャスト、ドラマ、アプリといった多様な顧客接点を設計しています。
例えば、読みものコンテンツ+商品の紹介を混ぜた「読みものタグ/お買いものタグ」の使い分けが行われており、潜在的なユーザーが「読みものを通じてブランド世界観に触れる → 購買行動へ移行する」という構造が実証されています。
また、Instagramでのハッシュタグ投稿や、ユーザー参加型イベント、スタッフインタビューといった、顧客とブランドの双方向コミュニケーションを意図した取り組みも実施されています。
クラシコムの特徴は、商品の販売そのものよりも「共感の共有」を目的にしたコミュニティマーケティングを展開している点にあります。
顧客はコンテンツや音声番組を通じてブランドの価値観に触れ、自身の生活と重ね合わせながらブランドとつながっていきます。企業側はその反応をもとに新しい企画を発信し、双方向の循環を育てています。
このように、世界観と理念への共感を軸にファンを育て、購買行動よりも「共感体験の継続」を重視する姿勢こそ、理念・ブランド共感型コミュニティマーケティングの代表的なモデルと言えます。
参考 / 画像引用:北欧、暮らしの道具店
事例⑥ CAMPFIRE
タイプ④ 理念・ブランド共感型

CAMPFIRE(キャンプファイヤー)は、2011年に設立された日本最大級のクラウドファンディング・プラットフォームで、創作者や社会活動家、企業がプロジェクトを立ち上げ、支援者(バッカー)がその希望を支える仕組みを提供しています。
2025年3月までに、累計で10万件超のプロジェクトと約1,300万人以上の支援者を記録しており、総調達額が1,000億円規模という公称データが提示されています。
このプラットフォームは、アイデアに共感する人々が集まり「支援」という形で関係を築く場として機能しており、単なる取引ではなく「共創・支持のコミュニティ」としての側面も持っています。
キャンプファイヤーの特徴は、プロジェクトを起点に「創り手(クリエイター)」「支援者(バッカー)」「プラットフォーム運営者」という三者で形成される関係性にあります。
この関係性は、企業と顧客の間に一方向的な取引ではなく、理念を共有しながら共に価値を生み出す「協働の関係」を生み出しています。
CAMPFIREのブランドが信頼を得ているのは、支援を「購買」ではなく「共感」として捉える仕組みを整えている点にあります。理念への共感を軸に、人々が自発的に関わり、相互に支え合う構造は、社会的意義を伴うコミュニティマーケティングと言えます。
参考 / 画像引用:クラウドファンディング – CAMPFIRE(キャンプファイヤー)
事例⑦ Snow Peak
タイプ① 体験・イベント型 / タイプ⑤ ロイヤルティ・会員型

新潟県三条市を拠点とするアウトドアブランド「Snow Peak(スノーピーク)」は、製品の提供にとどまらず、「自然と人をつなぐ体験」を通じてブランド価値を育てる戦略を展開しています。
同社は1998年からユーザー参加型イベント「Snow Peak Way」を継続的に開催し、顧客が社員と同じフィールドで交流しながら、製品の使用体験や改善提案を直接共有できる仕組みを整えています。
これらのイベントは単なる販売促進ではなく、顧客同士がつながり、ブランドの理念を体感するための場として機能しています。
また、会員制度では製品の購入だけでなく、キャンプ場利用や飲食などの体験を通じてもポイントが蓄積される仕組みを導入しており、オンラインとオフラインを横断して「ブランド体験の継続」を支える構造を築いています。
この制度は、顧客がブランドの世界観に共感し続けるためのインセンティブとして機能し、リピーター育成にも寄与しています。
スノーピークの取り組みは、リアルな接点を通じた体験・イベント型コミュニティマーケティングの要素と、メンバーシップによって関係を持続させるロイヤルティ・会員型マーケティングの要素を兼ね備えています。
ブランド体験を軸に、参加と継続の両面から顧客との関係性を深めるこの事例は、コミュニティマーケティングの理想的な複合形と言えます。
参考 / 画像引用:Snow Peak Way 2025
コミュニティマーケティングの実践における4つのポイント
コミュニティマーケティングは、単に「場を作る」だけでは長続きせず、目的の明確化・設計・運営・検証のすべてが連動して初めて効果が現れます。ここでは、コミュニティマーケティングを実践する際に意識すべき4つの重要なポイントについて解説します。
ポイント① ブランドの世界観に一貫性を持たせる
コミュニティの基盤となるのは「ブランドストーリー」です。コンテンツやデザイン、言葉づかい、発信のトーンに一貫性があることで、顧客はブランドの世界観に安心感と信頼を抱きます。
特に近年では、価値観でつながる「理念共感型」コミュニティが増えており、ブランドの軸が曖昧なままでは長期的な関係構築が難しくなります。
例えば、事例でも紹介した「北欧、暮らしの道具店」のように、世界観そのものを顧客との共通言語として設計することが重要です。
ポイント② 顧客が参加できる仕組みを設計する
コミュニティマーケティングの実践では、顧客が「関わる主体」になる仕組みが重要です。投稿やレビュー、共創イベント、ディスカッションなど、顧客が意見を発信できる場を設計することで、ブランドと顧客が双方向に価値を生み出します。
参加のハードルを下げ、顧客が自らの体験やアイデアを共有できる環境を整えることで、コミュニティが単なる情報発信の場から、共感と学びを得られる場になります。
重要なのは、参加頻度ではなく「関与の深さ」であり、顧客がブランドに貢献している実感を得ることで、持続的なエンゲージメントが生まれます。
ポイント③ コミュニティの運営体制を整え、熱量を維持する
コミュニティの管理者は、情報発信だけでなく、参加者の声を拾い、対話を促し、健全な交流を維持する重要な役割を担います。企業や組織が専任担当者を置き、社内外の関係者と連携しながら運営を継続することで、コミュニティの熱量を保つことができます。
また、ガイドラインや運営ポリシーを明文化し、安心して参加できる環境を整えることも、持続的な関係構築には不可欠となります。
ポイント④ 成果を可視化し、データで検証する
コミュニティマーケティングの価値を高めるには、感覚ではなくデータに基づいた検証が必要です。参加率や継続率、投稿数、UGC(ユーザー生成コンテンツ)などを定量的に把握し、運営改善に役立てることで、活動の成果が明確になります。
また、定量的なデータだけでなく、数値化できない「参加者の声」や「アイデアの反映度」などの定性的な評価も重要です。データ分析と人の感性を組み合わせることで、ブランドの成長を支えるマーケティング資産へと発展していきます。
まとめ
コミュニティマーケティングは、単発の施策ではなく中長期的なブランド戦略の一部として設計することが重要です。成功している企業に共通しているのは、「世界観の一貫性」「参加を促す仕組み」「継続的な運営」「データによる検証」という4つの柱を持っていることです。
こうした取り組みを継続することで、顧客との間に信頼とつながりが生まれ、結果としてブランドの成長やLTV(顧客生涯価値)の向上にもつながります。
もし、貴社のECのマーケティングを支援するパートナーをお探しなら、インターファクトリーのEC支援サービス「EBISU GROWTH」までお問い合わせください。経験豊富なコンサルタントが、EC事業者の課題を多角的に分析し、集客から顧客育成までを一貫して支援します。
◆EC支援サービス「EBISU GROWTH」の提供サービス
✓戦略立案
✓ECサイト構築
✓集客
✓CRM
✓アクセス解析・運用改善提案
✓運用代行・制作代行
顧客との関係性を深め、コミュニティを基盤としたマーケティングを実現したい企業にとって、信頼できるパートナーとなるはずですので、まずは下記サイトをご覧いただき、お気軽に資料請求をしてみてください。