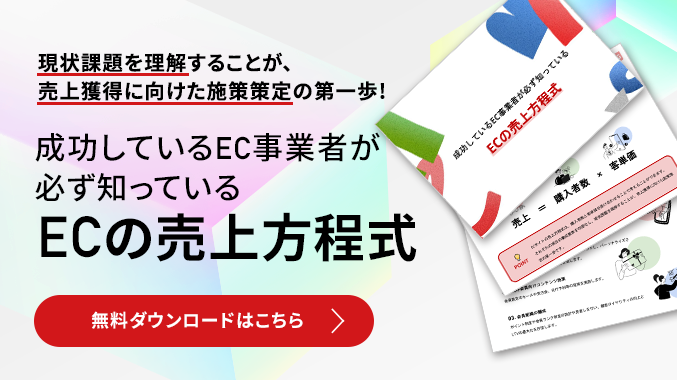「ECサイトはオープンソースで作れるのかな?」
「どのオープンソースがいいのかな?」
ECサイトをオープンソースのソフトウェアで作ることを検討してはいないでしょうか?
国内で実績のある有名なオープンソースは、以下の3つが挙げられます。
②Magento(マジェント)
③WordPress(ワードプレス)
オープンソースを使えば、ライセンスがフリーなので、サーバーにインストールして誰でも無料で利用すことができます。企業や技術力がある方がカスタマイズすることもできますし、カスタマイズしないでデフォルト機能だけでもECシステムを無料で用意することができるのです。
ただし、オープンソースでECサイトを作る場合は良いことだけではなく、オープンソースのセキュリティーの脆弱性について事前にを知識を得る必要があります。特に企業でECサイトを作る場合は、システムに脆弱性があることは大きな懸念となるはずです。
本日はインターファクトリーで、シニアアドバイザーを担当している筆者が、ECサイトのオープンソースで有名な3つのシステムと、オープンソースの注意点について詳しく解説いたします。
3つのECシステムのオープンソース
オープンソースは多くの会社から提供されていますが、日本国内であれば、下記の3つのオープンソースから選ぶべきでしょう。
①EC-CUBE(イーシーキューブ)
②Magento(マジェント)
③WordPress(ワードプレス)
オープンソースの決め手は、開発やECの設定に必要な情報がどのくらい手に入れられるか?という情報量が大切だからです。
それを考えると以下の紹介する「EC-CUBE」か「Magento」あるいは世界一のオープンソースのブログプラットフォーム「WordPress」のどれかが現実的です。
それでは、有名な3つのオープンソースを紹介します。
日本で一番のオープンソースはEC-CUBE(イーシーキューブ)
EC-CUBEは、日本国内で最も普及している国産のECオープンソースプラットフォームです。国内の開発事業者やSIerによる導入実績も豊富で、日本市場に特化した構造や、日本語での豊富な技術ドキュメントがあることから、国内向けECには非常に適しています。
多数の決済モジュール(クレジットカード、コンビニ決済、後払いなど)が公式・非公式ともに揃っており、業種や商材に応じて柔軟な機能拡張が可能です。また、定期購入や予約販売などに対応したプラグインも多く、D2C・単品通販サイトにも広く採用されています。
初心者でも導入しやすいように、大手レンタルサーバー各社には「クイックインストール機能」が用意されており、数クリックでサイト構築を始められる手軽さも魅力です。
一方で、自由度が高い分、セキュリティ面には注意が必要です。過去に情報漏洩や脆弱性が報告された事例もあり、運用にあたっては開発知識やセキュリティ対策の実装が求められる点も念頭に置くべきでしょう。
世界一のオープンソースはMagento(マジェント)
Magentoは、米Adobe社が提供している世界No.1のシェアを誇るオープンソース型ECプラットフォームです。中〜大規模のECサイトを想定して設計されており、BtoBや越境ECなど、複雑な商流・多拠点対応を求められるビジネスにおいて高い評価を受けています。
多言語・多通貨対応が標準で実装されている点が最大の強みで、アジアや欧米など、複数国での販売を視野に入れた展開を行う企業にとっては心強い選択肢です。また、PayPalやStripeなど海外で主流の決済手段との親和性も高く、スムーズな国際取引が可能です。
管理画面は日本語化モジュールを導入することでローカライズでき、日本語ユーザー向けのフォーラムも存在しますが、最新情報や高度な技術知識は英語圏の情報に依存する場面も少なくありません。そのため、社内にエンジニアリソースがある、または外部ベンダーと連携できる体制がある企業向けです。
EC構築におけるカスタマイズの自由度が非常に高いため、自社仕様の複雑な業務フローや在庫管理、独自のUI設計を求める場合に特に有用です。
WordPress(プラグインのWelCart(ウェルカート)を使ってECを運営)
WordPressは、世界中で最も使われているオープンソースのCMS(コンテンツ管理システム)であり、日本でも高いシェアを誇ります。このWordPressに、EC機能を追加するプラグイン「WelCart(ウェルカート)」を導入することで、手軽にECサイトを構築することができます。
すでにWordPressを用いてオウンドメディアやブログを運用している企業であれば、既存の集客導線をそのまま活かしながらEC展開ができる点が大きなメリットです。WelCartは、単品通販や小規模なショップに最適化されており、軽量でシンプルな設計が特徴です。
プラグイン開発元のサポート体制や専用フォーラムも整備されており、情報収集やトラブル対応も比較的スムーズに行えます。また、WelCart専用のテーマや拡張プラグインも存在し、必要に応じた機能拡張も可能です。
一方で、WordPress自体がブログ向けに最適化されたCMSであるため、商品点数が多い総合ECサイトや、大規模な在庫管理が必要なケースでは、運用の限界が出てくる場合もあります。そのため、比較的ライトな構成のECサイトに向いています。
オープンソースだからと言って、完全に無料ではない!
オープンソースであっても、以下のような費用がかかります。
◆オープンソースにもかかる費用の一覧
①サーバー費用
②ドメイン取得費用
④デザイン費用
④決済手数料
それでは一つずつ解説してまいります。
①サーバー費用
無料ライセンスのオープンソースは、そのソフトをいかように使っても、使用料は発生しません。しかし、ECサイトを構築するとなると、サーバーが必要です。個人や企業でも、レンタルサーバーでECサイトを作る人が多いでしょう。
レンタルサーバーの費用相場:月間1,500円~数万円
②ドメイン取得費用
ECサイトのドメインを取得する費用がかかります。ドメインの取得方法は3つあります。
◆ドメインの取得方法
①お名前ドットコムのような専門サイトから購入する方法、
②契約したサーバー経由で契約する方法、
③中古ドメインを取得する方法
もし、管理を楽にしたいのであれば、2つ目のサーバー経由で契約する方法がおススメですが、将来ECサイトを第三者に売却などしたい場合は、①か③がおススメです。中古ドメインの購入はSEOを上げるために選び方が多いのですが、中古ドメインはGoogleも推奨しておらず、SEOに独自のノウハウをお持ちでなければやめておくべきでしょう。
どの方法を選んでも費用は数千円程度となります。
サーバー費用は年間千円程度
③デザイン費用
オープンソースには最初からデザインテンプレートが用意されていますし、無料で公開されたテンプレートをダウンロードして使うこともできますから、費用をかけなくてもECサイトをオープンすることができます。しかも無料だからといって、質が低いわけではなく、見た目は立派なECサイトが作れます。
しかし、デザインにこだわりたい方は、デザイナーを入れると費用は20万円~100万円くらいかかりますし、有料のテンプレートを使うと費用がかかります。有料のテンプレートの費用の目安は1~2万円のものが多いです。
テンプレートはほぼ、全てがレスポンシブル対応になっているので、スマホ対応も問題ありませんので、デザイナー費用を捻出できない場合は、テンプレートを利用します。
④決済手数料
オープンソースでECサイトを構築した場合でも、注文処理時には決済手数料が必ず発生します。特に主流であるクレジットカード決済では、1件あたりの決済金額に対して約3〜5%前後の手数料が発生するのが一般的です。決済代行会社によっては、取扱高や業種によって料率が上下することもあります。
この手数料は成果報酬型(従量課金)であることが多く、基本的に月額の固定費がかからないケースもありますが、一部の決済代行サービスでは初期費用や月額利用料が発生することもあるため注意が必要です。
また、決済方法の種類によっても手数料が異なるため、クレジットカードのほか、コンビニ決済や口座振替、PayPayなどのスマホ決済を導入する場合は、それぞれのコスト構造を事前に確認しておくと安心です。
無料のオープンソースでも、「決済に関わる手数料」は運営上のコストとして確実に発生するため、商品価格や利益率の設計にあらかじめ組み込んでおくことが重要です。
オープンソースをカスタマイズして再販売することもできる!
また、オープンソースによっては、カスタマイズを行い、独自のパッケージとして販売することができます。
実際に国内で有名なオープンソースのEC-CUBEをカスタマイズして、自社のパッケージとして販売しているベンダーは数多くいますし、顧客からECサイトの要望があれば、ITベンダー(ECが専業ではない)がEC-CUBEをカスタマイズして、ECサイトを作ることもよくあります。
自分達で内製すれば、ライセンス費用が無料になりますが、再販売されたオープンソースは、普通のECパッケージとして販売されるため、数百万円~数千万円の中・大規模向けのECシステムとして使われることが多いです。
オープンソースの注意点1:セキュリティー
有名なオープンソースほど、ハッカー間でシステムの脆弱性の情報が出回りやすく、ハッキングされやすい傾向があります。オープンソースのWordPressは世界中でサイト改ざんされており、WordPressの導入を禁止する企業もあります。2017年には過去最悪級のサイト改ざん被害がありました(筆者も被害にあいました)。
また、EC-CUBEですが、経済産業省から脆弱性について注意喚起されており、それくらいセキュリティー対策をしっかりしないといけないのです。
このようにオープンソースを使う場合に気をつけなくてはいけないのは、常に最新のバージョンをインストールして、脆弱性に備える必要があります。
しかし、オープンソースの弱点はまさにこの点です。例えば、一度カスタマイズしたワードプレスには最新のバージョンをインストールすることは出来なくなります。
またECサイト運営者の立場で考えると、最新のバージョンをいれるのを嫌がるユーザーも多くいます。なぜなら、ECサイトの運営で機能拡張のために、多くのプラグインをいれているケースがあり、最新のオープンソースのバージョンにプラグインが対応していない場合があるのです。
ですからユーザーも、少し様子を見てから最新のバージョンをインストールする傾向があります。
最新のバージョンを積極的に利用するには、オープンソースを定期的にバックアップするしかありません。また顧客のデータが失われるのを防ぐ意味でも、ECシステムのバックアップを定期的にとりましょう。
ここまでが、個人でオープンソースを使う場合の注意点で、次に企業の注意点を解説します。
オープンソースの注意点2:再販売されたオープンソースの契約書
企業のECサイトとなると、初期費用に数百万円~数千万円かかる、中・大規模のECサイトとなります。これくらいの規模のECサイトになると、オープンソースに関して言えば、自社内でオープンソースを内製してつくるケースより、ベンダー企業がオープンソースをもとに開発したECパッケージを使うケースがほとんどです。
もし、ベンダーがオープンソースをカスタマイズして作ったパッケージを販売している場合は、次の点に注意が必要です。
障害は誰の責任?オープンソース提供元?ベンダー?自社?
例えば、オープンソースをもとに開発した、ベンダーが発売したECシステムを使ってECシステムを運営しているとしましょう。
もし、顧客の情報漏えいのような大きな障害があった場合、システムの責任はどこになるでしょうか?実は自社になる可能性が高いのです。
まず、オープンソース提供元には責任はありません。なぜならオープンソース提供元は無償でプログラムコードを開示しているだけで、自社と商契約を結んでおりませんので、オープンソース提供元の責任になることはありません。(これは当たり前ですよね。)
では、ベンダーでしょうか?いえベンダーが「この障害は、我々が作ったプログラムではなく、オープンソースそのものの障害です。ですから責任はありません。」というケースがあります。そして契約書をよく見ると、このような一文が必ず書かれているはずです。
こうなると、オープンソース提供元もベンダーも責任を取らないので、自社で責任を取るしかありません。実は過去にこういった経緯で、裁判になるケースが多々あります。詳しくは下記の記事をご覧ください。
オープンソースの注意点3:一定のITリテラシーが求められる
オープンソース型のECシステムは、自由度が高く、カスタマイズ性に優れる一方で、システムの導入・運用には一定のITリテラシーが求められる点に注意が必要です。
近年では、各種プラグインやテンプレートが充実しており、見た目の変更や機能追加といった基本的なカスタマイズであれば、プログラミング知識がなくても対応可能なケースも増えています。しかし、これらのプラグインの選定や設定には、ある程度の専門用語の理解や、システム構造の把握が必要です。
また、カスタマイズの途中で不具合が発生したり、他の機能と競合したりする場合、トラブルシューティングや保守対応を自力で行うスキルが必要になります。ITリテラシーが十分でない場合、たとえ簡易的な変更であっても、都度開発会社やエンジニアに依頼する必要が生じ、時間的・金銭的コストがかさむこともあります。
そのため、オープンソースを活用する際には、社内にある程度の知識を持った担当者がいるか、外部パートナーと円滑に連携できる体制があるかを事前に確認しておくことが、スムーズな運用のカギとなります。
オープンソースでECサイトを作る前に「そもそも、その商品は売れるのか?」
ECサイトを作る前に考えて欲しい点は、マーケティングです。なぜならECサイトは作るのはカンタンですが、集客するのがものすごく大変なのです。
例えば、あなたが自社ECサイトで、NIKEの靴を売るとしましょう。では、あなたのECサイトで、NIKEの靴を買う人がいるでしょうか?下記の3つの課題があります。
①あなたのECサイトをユーザーは発見できない
②NIKEの公式ECサイトやAmazonで買う
③あなたのECサイトは有名ではないから買うのをためらう
まず、「ナイキ スニーカー」や靴の型番で検索しても、あなたのECサイトが検索エンジンで上位に立つことは困難です。代わりに、NIKEや楽天、Amazonなどの有力ECサイトが検索結果の上位に出てきます。あなたのECサイトが発見されるのはカンタンなことではありません。
商品が他のECサイトでも買えるのなら、ユーザーは慣れている大手のECサイトで商品を買うことになるでしょう。わざわざ有名ではないECサイトで商品を買う人はほぼいません。
また、なんとか、あなたのECサイトに辿り着いたユーザーであっても、ほとんど商品は売れません。なぜなら有名ではないECサイトだと「このサイトにクレジットカード番号を入力したくないな。。」と思われてしまうからです。
しかし、このような状況でも、あなたのECサイトでしか売っていないものがあれば売れるかもしれません。こういったモノだと売れる可能性は高いでしょう。下記はSNSをキッカケに話題になった”高知の財布”ですが、高級ブランドのコーチをもじったもので、このECサイトでしか買えません。
このような独自の商品があれば、ECサイトへの集客が可能で売ることができますが、商品力やマーケティング力がないと、ECサイトで商品はなかなか売れません。
オープンソースよりも手軽な無料のECシステムがある!
もし、ECシステムを無料で作りたいということでしたら、もっと手軽な無料のASPがあります。それがBASEとSTORESです。
これらのASPは、SNSのプロフィール設定くらいの労力でECサイトを作ることもできますし、無料プランであれば費用は決済手数料しか、発生しません。デザインテンプレートも用意されているため、ITリテラシーに自信がない方でも、立派なECサイトをすぐにリリースすることができます。
自分でカスタマイズしたい!ということにこだわりがないのでしたら、BASEやSTORESの方が、カンタンにECサイトを作ることができます。小規模企業のECサイトとして、よく使われております。
オープンソースのまとめ
オープンソースのECシステムの選び方は、まずはフォーラム等で開発や設定に関する情報が豊富にあることが前提になってきますので、EC-CUBEとMagento以外は、採用する意味合いが少ないと思います。
そして、オープンソースがゆえに脆弱性に付け込まれることがあるため、バージョンをアップデートして、最新の状態を保ちましょう。さらにバックアップも定期的とることができれば、ためらいなく最新版にアップデートすることができます。
企業がオープンソースを採用する場合は、障害発生時に問題にならないように、契約書の確認をしっかり行いつつ、ECパッケージや、クラウドECの採用も考えてみましょう。
年商1億円以上のサイトになる場合は、セキュリティー対策が万全な弊社のフルカスタマイズできるクラウドのECプラットフォームの「EBISUMART」も検討してみてください。興味ある方は下記のホームページをご覧ください。